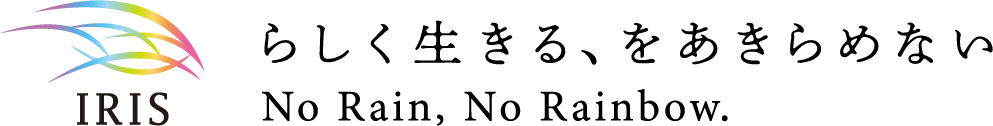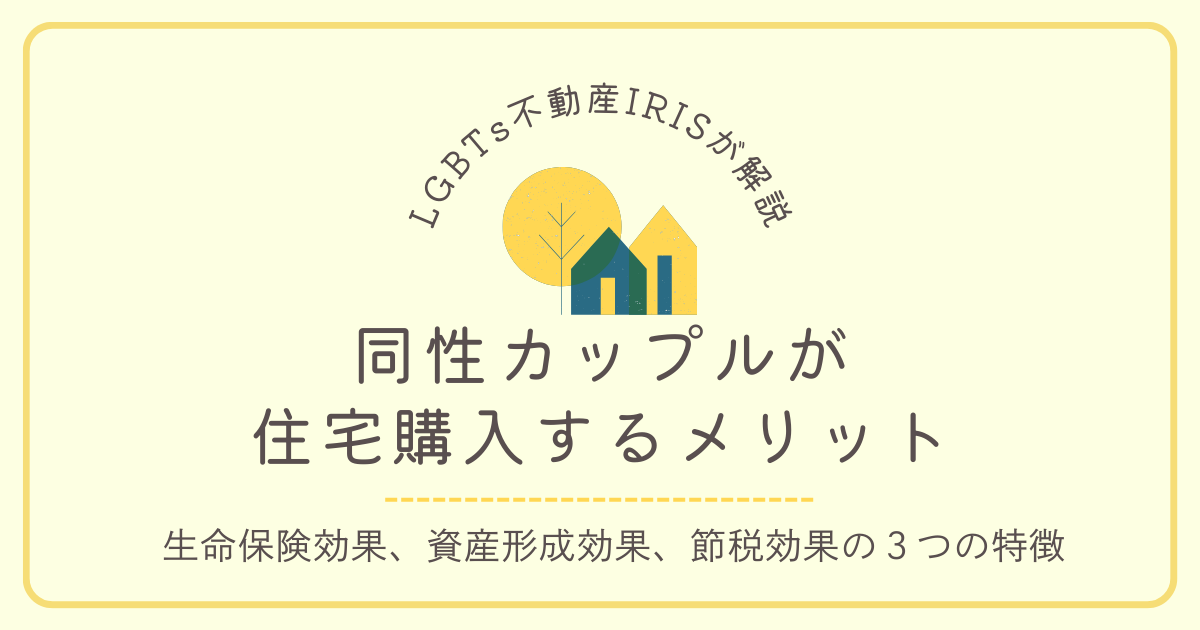
はじめに
近年、日本においても同性カップルに対するサービス展開が増え、多様性を尊重する社会への変化が加速しています。2015年の渋谷区パートナーシップ条例制定を皮切りに、現在(2025年6月30日)では538もの自治体がパートナーシップ制度を導入しており、同性カップルの住宅購入に関する環境も大きく改善されています。
LGBTsフレンドリーな不動産会社であるIRISでも、多くのお客様に住宅を購入いただいています。
住宅購入は単なる居住空間の確保にとどまらず、生命保険効果、資産形成効果、節税効果という三つの重要な経済的メリットも存在しています。
これらの効果を最大化するためには、同性カップル特有の法的・税制的課題を理解し、適切な戦略を構築することが必要になります。
この記事ではこのテーマについて詳細に解説していきます。
1. 生命保険効果について
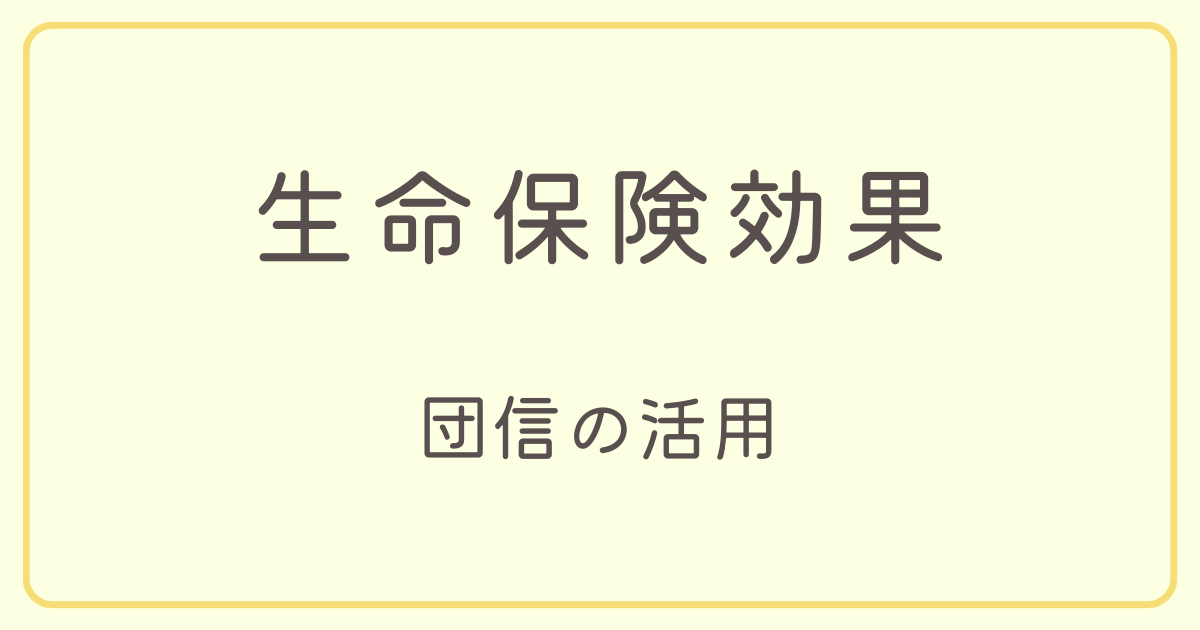
団体信用生命保険の活用
住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)は、債務者が死亡または高度障害状態になった場合にローン残債が完済される仕組みです。同性カップルの場合、なにも対策を行わなければ法定相続人となることができないため、この効果は大きな役割を果たします。
住宅ローンに付帯する団信は、多くの金融機関で加入が必須条件となっています。民間銀行では団信加入を融資条件とする場合が多いため、ほぼ100%に近い加入率となっていることが想定されます。
会計検査院の調査によると、団信加入が任意である住宅金融支援機構(フラット35)でも団信加入率は73.8%(平成25年度)となっていました。
団信の保障額は住宅ローン残高に相当し、数千万円規模の生命保険に相当する保障効果があります。 (参考:会計検査院 平成26年度決算検査報告)
同性カップルにとっての団信
同性カップルにとって団信は、具体的なメリットとなり得ます。具体的なケースで見てみましょう。
【ケース例】AさんとBさん(30代同性カップル)が3,500万円の住宅を共同購入
- 借入金額:3,500万円(Aさん2000万円、Bさん1500万円)
- 住宅ローンの形態:ペアローン
- 所有割合:Aさん6割、Bさん4割の共有
- 月々返済額:約12万円
- 団信の形態:連生型団信
もしAさんに万が一のことがあったとき
連生型団信に加入している場合
確実な住居確保:住宅ローンの残債の全額が自動的に完済されるため、Bさんは法的相続関係がなくても安心してその家に住み続けることができます。
仮に相続対策をしていなくても、Aさんの法定相続人(両親など)との共有関係が新たに形成されるため、一方的に立ち退きを強要されることはありません。ただし、相続対策をしていない場合、法定相続人に対して何らかの金銭補償をする必要が生じる場合があります。
大幅な経済負担軽減:月々12万円の住宅ローン返済がなくなることで、Bさんの年間支出は144万円軽減されます。
このように、団信は同性カップルにとって「住まいと経済的安定を同時に守る」極めて重要な保障となります。ただし、同性カップルの場合、通常パートナーは法定相続人ではないため、遺言書の作成などにより、確実な財産承継を図る必要がありますが、IRISでは、司法書士や弁護士・税理士と連携し、住宅購入と同時に適切な相続対策を相談することが可能です。
疾病保障特約の重要性
近年の団信では、がん、急性心筋梗塞、脳卒中などの三大疾病に加え、八大疾病や就業不能状態をカバーする特約が充実しています。同性カップルは将来的な介護や医療における意思決定権限が制限される可能性があるため、無視できない要素と言えます。
疾病保障特約付き団信の利用率は年々増加しており、特に同性カップルの場合、パートナーが医療意思決定に関与できない可能性を考慮し、公正証書による任意後見契約の締結と併せて、包括的な保障を確保することが重要となります。
2. 資産形成効果について
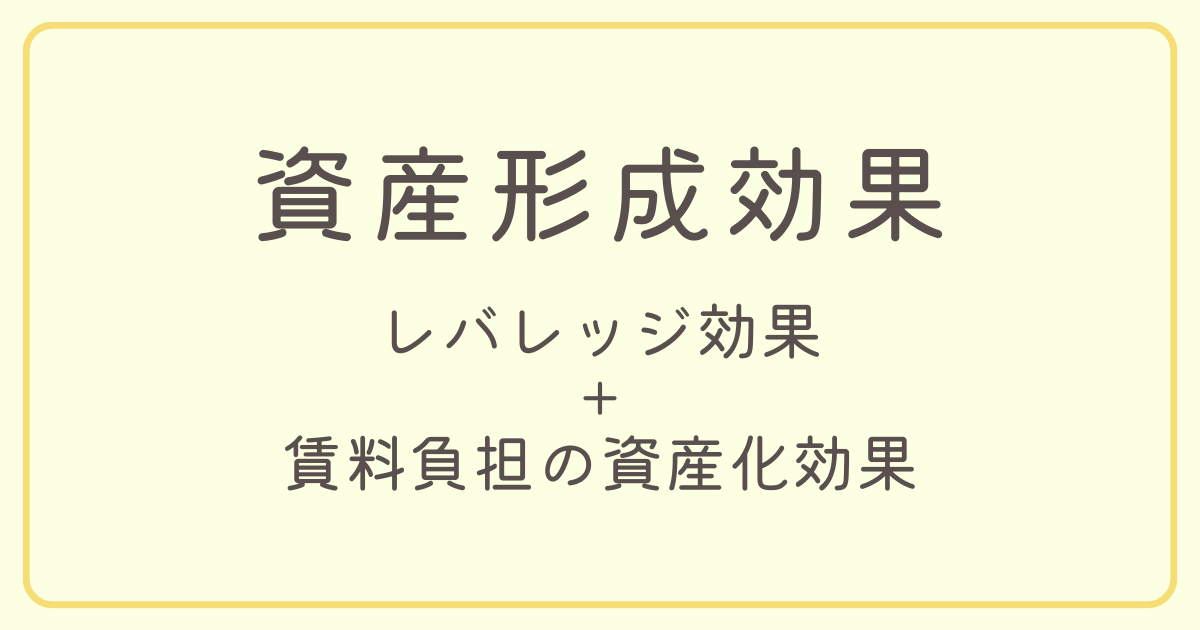
借入金を活用した資産形成
住宅購入の最大の魅力は、他人の資本(住宅ローン)を活用して資産を形成できることです。例えば、4,000万円の住宅を頭金400万円、住宅ローン3,600万円で購入した場合、自己資金400万円で4,000万円の資産を手に入れることができます。これは投資における「レバレッジ効果」と同じ原理です。
具体例:Aさん・Bさんカップルの資産形成
- 購入価格:4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)
- 自己資金:400万円
- 住宅ローン:3,600万円(35年返済)
建物の残存価値と土地の資産性
建物は減価償却により価値が下がりますが、適切にメンテナンスされた住宅は長期にわたって相当な残存価値を保ちます。木造住宅でも築20~30年で一定の価値を維持し、鉄筋コンクリート造マンションなら50年以上の耐用年数があります。毎月の住宅ローン返済により元本が減る一方で、建物資産は手元に残り続けます。
土地は需要の変化などにより値段の上がり下がりがある一方で、原則として価値が一方的に減少していくことがない資産です。特に首都圏では顕著な地価上昇が続いています。2024年の公示地価発表によると、東京圏の住宅地は前年比3.4%上昇し、3年連続で上昇幅が拡大しています。
具体的な上昇エリアとしては以下のようなエリアがあげられ、地価上昇の要因は以下のように考えられます。
上昇率の高いエリア(2024年基準地価)
- つくばエクスプレス沿線:流山セントラルパーク駅、流山おおたかの森駅が上位3-4位にランクイン
- 城北エリア:豊島区(7.8%上昇)、文京区(7.4%上昇)、荒川区、北区
- 都心部:中央区(7.5%上昇)、港区(7.2%上昇)、目黒区(7.3%上昇)
- 再開発エリア:綱島(東急新横浜線開通効果)、立川(中央線沿線ターミナル)
(参考:住まいの情報館 2024年公示地価分析、住まいの情報館 基準地価ランキング、プレスリリース 地価動向分析)
地価上昇の要因
- 交通利便性:都心への直通アクセス、新線開業
- 再開発プロジェクト:駅周辺の大型開発、商業施設整備
- 生活利便性:商業施設充実、子育て環境の良さ
- 需給バランス:限られた供給と堅調な住宅需要
同性カップルの場合も、将来的な資産性を重視したエリア選択により、購入時より高い価格での売却や、ローン完済後には賃貸経営による収益確保も期待できます。IRISでは、資産性の高い物件選定から、同性カップルに適した共有名義や遺言書の活用まで、包括的な相談が可能です。
賃料負担の資産化効果
また、副次的な効果ではありますが、賃料負担がそのまま積み立てとなる、資産化効果があげられます。
総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、賃貸住宅の1か月あたりの平均家賃は約5万5,695円となっていますので、これをベースに算出します。 (参考:総務省統計局 住宅・土地統計調査)
賃貸と持家の35年間比較
- 賃貸の場合:月5.6万円×35年=約2,350万円の支出→手元に何も残らない
- 持家の場合:住宅ローン返済→建物・土地という資産が手元に残る
また、同性カップルの場合、賃貸物件の契約において選択肢が狭まってしまうリスクがありますが、持家取得によりこうした問題から解放されます。また、将来的な住み替えや賃貸経営への転換も視野に入れることで、さらなる資産活用が可能になります。
リバースモーゲージの活用可能性
さらにダメ押しになりますが、高齢期における資金調達手段として、住宅を担保とするリバースモーゲージが注目されています。同性カップルの場合、法的な相続人がいないケースが多いため、この制度の活用メリットがより大きくなる可能性もあります。
3. 節税効果(税制優遇の最大活用)
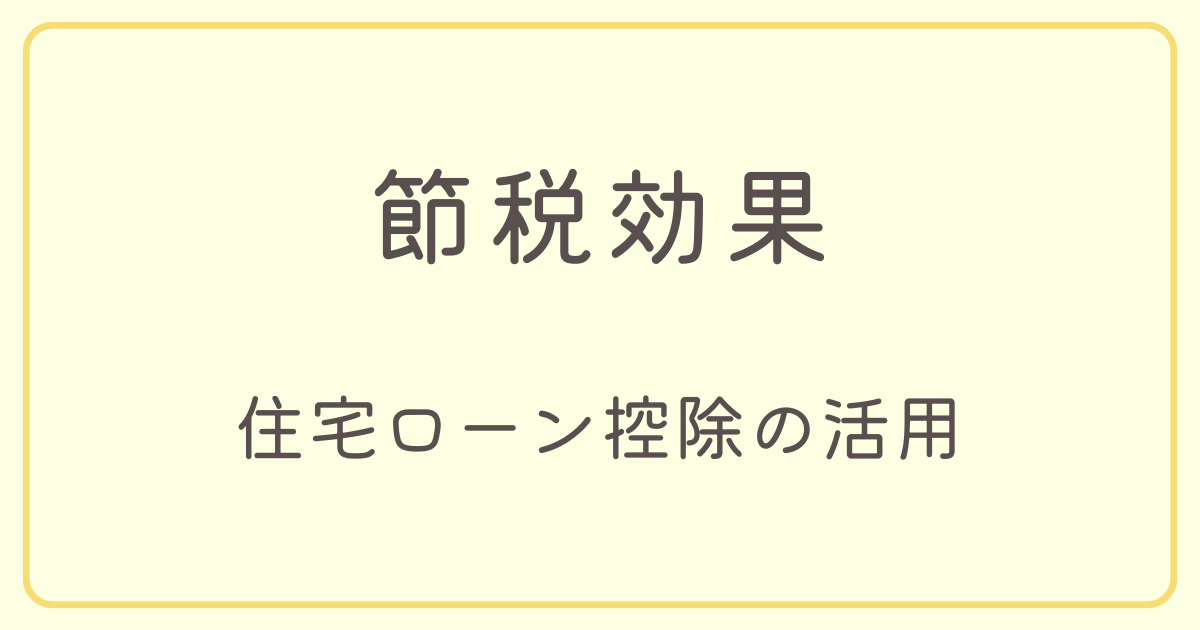
住宅ローン控除の活用
住宅ローン控除は、年末ローン残高の0.7%(最大控除額は住宅性能により21万円~35万円)を13年間所得税から控除できる制度です(2025年現在)。2024年度の制度改正により、省エネ性能に応じて控除額が決定されるようになりました。 (参考:国土交通省 住宅ローン減税)
同性カップルが共有名義で住宅を購入する場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることができ、世帯全体での節税効果を最大化できます。例えば、3,000万円の住宅を1,500万円ずつのローンで購入した場合、両者合わせて年間最大42万円の控除を受けることが可能です。
新築住宅の2024年度住宅ローン控除の借入限度額
- 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4,500万円
- ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
- 省エネ基準適合住宅:3,000万円
- その他の住宅:省エネ基準を満たさない場合は対象外(一部例外あり)
中古住宅の住宅ローン控除 中古住宅の場合、新築住宅と比べて適用条件が緩和されており、同性カップルにとってより利用しやすい制度となっています。
- 借入限度額:一律3,000万円(住宅の性能に関わらず)
- 控除期間:10年間
- 省エネ基準:中古住宅には省エネ基準の適用なし
- 築年数制限:撤廃され、新耐震基準適合が条件
さらに中古住宅を売買する場合、消費税課税取引(業者売主)なのか、消費税非課税取引(個人間売買)なのかによって、住宅ローン控除の適用において違いがあります。
消費税課税取引(業者売主)の場合
- 新築・中古問わず、上記の借入限度額が適用
- 中古住宅なら3,000万円まで
消費税非課税取引(個人間売買)の場合
- 住宅ローン控除の借入限度額が2,000万円に制限される
- 年間控除額は最大14万円(2,000万円×0.7%)
- 10年間で最大140万円の控除効果
この制限は、個人間売買では消費税が課税されないことから、消費税相当分の負担軽減が既に図られているという制度設計によるものです。
同性カップル向けの活用例
共有名義で2,000万円の中古住宅を1,000万円ずつのローンで個人間売買により購入した場合:
- 各パートナーが年間最大7万円の控除(1,000万円×0.7%)
- 世帯合計で年間最大14万円、10年間で最大140万円の節税効果
- 個人間売買のため建物部分に消費税は非課税
同性カップルが共有名義で住宅を購入する場合、それぞれが住宅ローン控除を受けることができ、ペアローン利用の場合は世帯全体での節税効果を最大化できます。ただし、個人間売買の場合は控除上限が制限されることを考慮した資金計画が重要です。
4. IRISを利用するメリット(LGBTsフレンドリー不動産の特徴)
専門知識を活用したお客様へのサポート
同性カップルの住宅購入では、一般的な法律婚上の夫婦のケースとは異なる法的・税務的課題に対する専門的な対応が不可欠です。IRISでは、これらの課題を深く理解した専門スタッフが、お客様のライフプランに最適なご提案を提供します。
相続リスク対策
- 司法書士との連携による遺言書作成サポート
- パートナーシップ制度の活用による権利保護強化
- 任意後見契約の活用による将来的な生活リスクへの対処
共有物分割リスク対策
- 共有持分の適切な提案
- 将来的な住み替えを考慮した物件選択の提案
いずれにパターンにおいても、IRIS独自のノウハウに加えて、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等との連携により、ニーズに合わせてサポートのレベル感や強度を適切に設定することができます。
相続については以下の記事でも解説しています。
LGBTsフレンドリーな接客環境
IRISは、LGBTs当事者またはアライ(理解のあるストレート)のスタッフのみで構成された、LGBTsフレンドリー不動産会社です。2014年の創業以来、延べ10,000件以上のお部屋を紹介してきた豊富な実績を持ち、同性カップルの住宅購入における様々な課題を深く理解しています。
当事者目線での安心できる相談環境
IRISでは、スタッフ全員がLGBTs当事者またはアライと明言しており、お客様と同じ目線で真に理解のある相談を提供しています。カミングアウトしていない場合の年齢差があるカップルや外国籍のカップルであっても、複雑な説明や理由付けを求められることなく、自然体で住宅購入の相談を進めることができます。
また、審査から契約まで一貫してアウティングに配慮しており、お客様の情報を確実に守る体制を整えています。このような環境だからこそ、多くの同性カップルが安心してライフプランについて率直に相談いただけているものと理解しています。
金融機関との緊密な連携体制
IRISでは、複数の金融機関と提携することにより、同性カップルが住宅ローンを利用する際の書類作成から申込・審査に至るまで、一貫したサポート体制を構築しています。従来の不動産会社では、金融機関への橋渡し程度に留まることや、そもそも紹介自体をしないことが多い中、IRISは金融機関に対して細やかに連携することで、お客様が複雑な手続きに悩むことなく、スムーズな融資実行をサポートしています。
このような連携により、同性パートナーを配偶者と同等に扱う住宅ローン商品について最新の条件や審査基準を把握し、お客様お一組ごとの状況に最適な金融機関とローン商品をご提案可能となっています。また、審査時に生じがちな同性カップル特有の説明や書類不備についても、事前に金融機関と調整を行うため、お客様にご負担をおかけすることなく円滑な手続きが可能です。
融資条件の最適化
共有名義での住宅購入において、両パートナーがそれぞれ住宅ローン控除を受けられるよう最適な名義設定をサポートし、疾病保障特約を含む団信の選択から、将来のライフステージ変化を考慮した柔軟な返済計画まで、総合的な融資条件のヒアリングとご提案も行っています。
5. お客様の声
埼玉県越谷市で購入されたカップルの事例(30代40代女性カップル)
埼玉県越谷市で新築戸建てを購入されたお二人は、10年間の賃貸生活から「猫ファースト」の価値観を大切にした住宅購入を実現されました。4匹の愛猫と自由に、制約なく過ごせる住環境を求めて戸建て購入を決断し、現在は駅徒歩6分の静かな住宅街で理想の暮らしを送られています。
購入の決め手とプロセス
当初はペアローンでの住宅購入を希望されていましたが、パートナーシップ制度の利用タイミングや具体的な手続きについて不安を抱えていらっしゃいました。しかし、IRISでの相談により、「何も隠さずに全部考えていることをお話できた」「カミングアウトしていない状況でのしんどさが全くなかった」という安心できる環境で住宅購入を進めることができました。
担当による銀行担当者との密なやり取り、行政書士や保険会社への丁寧な連携により、転職というデリケートなタイミングでの住宅ローン申請も適切にサポート。当初諦めかけていた「築年数が新しく、駅に近い」という両方の条件を満たす理想の新築戸建てを見つけることができました。
神奈川県横浜市で購入されたカップルの事例(30代40代女性パートナー関係)
神奈川県横浜市で中古マンションを購入されたお二人は、一方がトランスジェンダーで外国籍、もう一方が日本国籍という同性パートナー関係で、在宅勤務に適したより広い住環境を求めて2年間の困難な物件探しを経験されました。
購入前の困難な体験
一般的な不動産ポータルサイトでは「築50年の木造アパートか、月30万円を超える高級物件」という極端な選択肢しかなく、「普通の予算で、普通の希望を叶えてくれる物件が見つからない」状況でした。さらに、ある不動産会社からは「女性同士だと審査が通らないから、男性親族との偽装同居なら審査通りますよ」という提案を受け、「ありえないな、と思いました」「2人の関係性が尊重されない形で、システムに屈する形で契約をするのは、絶対に受け入れがたい」という心境に至りました。
IRISでの安心できるサポート
IRISでの初回相談では「そこを一切触れられなかった。ごく自然に接してくれて」「カミングアウトしなくても家探しができる」という新鮮な体験を得られました。担当者による専門的な知識と理解により、複数の課題(外国籍、トランスジェンダー、収入面の不安、同性パートナー関係)を一つ一つ丁寧に解決していくことができました。
そして、賃貸ではなく購入も可能であるという見通しが立ったため、横浜市の物件を購入するに至りました。富士山の見える窓辺で心地よい日々を送り、「この環境自体が穏やかなので、この生活が維持できたらいい」と満足されています。
まとめ
同性カップルの住宅購入は、生命保険効果、資産形成効果、節税効果という三つの大きなメリットが存在します。これらの効果を最大化するためには、同性カップル特有の法的・税務的課題を理解し、適切な専門家のサポートを受けることがより望ましいと言えるでしょう。
LGBTsフレンドリーな不動産会社IRISは、多様性を尊重し、お客様一人ひとりのライフプランに最適化された住宅購入をサポートいたします。専門知識を活用したご提案、多様性を尊重した接客体制、金融機関との強固なパートナーシップにより、同性カップルの皆様が安心して住宅購入を実現できる環境を提供いたします。
住宅購入は人生における最重要な決断の一つです。IRISでは、同性カップルの皆様が直面する様々な課題に対して、専門的な知識と豊富な経験を基に、お客様の幸せな未来の実現に向けて、私たちが全力でサポートいたします。