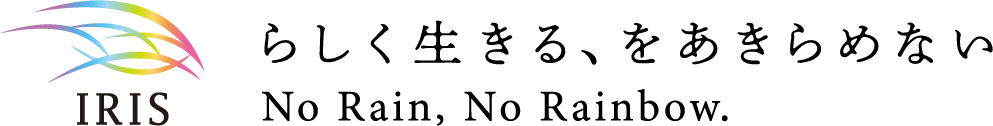2023年、アウティング禁止条例を持つ自治体の数が急増しています。2018年に東京都国立市が先駆けとなり、アウティングの禁止を明文化した条例を制定したことが記憶に新しいです。
その背景には、一橋大学の悲劇的な出来事があり、それがアウティング問題の認知を高めるきっかけとなりました。そして、その後の数年間で、多くの自治体がこの問題に取り組むようになりました。
今回の記事では、アウティング禁止条例の現状や、それに関連する最新の動向について詳しくご紹介いたします。
| 初めに |
|---|
| IRISでは、あらゆるマイノリティが暮らしやすくなることを目指すという意味から「LGBTs」と表記していますが、今回は一般的な「LGBT」について解説するため、表記が混在しております。 |
アウティング禁止条例の背景
アウティングとは、LGBTsの方の性的指向や性自認を、その方の同意なく他者に公開する行為を指します。この行為は、当事者に深い心の傷を与えることが多く、社会問題として注目されてきました。
2018年4月1日、東京都国立市がアウティングの禁止を明文化した初の条例を制定しました。この動きは、多くのメディアで取り上げられ、社会的な話題となりました。しかし、この条例制定の背景には、悲しい出来事が隠されていました。
2016年、一橋大学法科大学院の学生が、同級生からのアウティングを受けたことが原因で、校舎から飛び降りて命を絶ったという悲劇が発生しました。この事件は、アウティングの問題がどれほど深刻であるかを多くの人々に知らしめることとなりました。そして、この学生さんのご遺族が裁判を起こし、アウティングの問題が一層世間に認知されるきっかけとなりました。この事件が起きた一橋大学の校舎がある国立市が、全国で初めてアウティングの禁止を条例に盛り込むこととなったのです。
このように、一つの条例が制定される背景には、多くの犠牲や努力、そして社会の変化が隠されています。アウティング禁止条例の背景を知ることで、私たちはこの問題に対する理解を深め、より良い社会を築く手助けとなることを願っています。
アウティング禁止条例の現状
アウティング禁止条例の制定は、国立市の取り組みを皮切りに、全国各地で広がりを見せています。特に近年、この問題への認識が高まる中で、多くの自治体が条例の制定を進めています。
国立市の条例制定から数えて3年の間に、アウティング禁止を明記した自治体は急増しています。具体的には、2020年には5自治体でしたが、2023年10月1日時点で、少なくとも12都府県で26自治体がアウティング禁止を条例で明記しています。これは、わずか3年間で約5倍に増加した計算となります。
東京都国立市をはじめ、武蔵野市、町田市、日野市、豊島区、港区、江戸川区、杉並区、墨田区など、多くの自治体がアウティング禁止を謳う条例を制定しています。また、埼玉県深谷市、神奈川県逗子市、静岡県富士市、愛知県岡崎市、三重県いなべ市、京都府福知山市、兵庫県宍粟市、岡山県総社市など、都市部だけでなく、地方の自治体もこの取り組みを進めています。
しかし、アウティング禁止条例の制定は、まだまだ全国の自治体に広がっているとは言えません。多くの自治体がLGBTs差別禁止を謳う条例を持っている中で、アウティングに関する規定がない場合も少なくありません。この現状を踏まえ、今後の取り組みがより一層求められています。
アウティングとLGBTs差別禁止
アウティング禁止条例の制定が進む中、LGBTsに対する差別禁止の取り組みも各地で進められています。しかし、両者は必ずしも一致しているわけではありません。実際、同性パートナーシップ証明制度を導入している自治体であっても、アウティング禁止条例が存在しない場合があります。
例えば、同性パートナーシップ証明制度をいち早く導入した自治体の中には、アウティングに関する規定がないものも少なくありません。これは、LGBTs差別の禁止とアウティングの禁止が、異なる課題として捉えられていることを示しています。LGBTs差別の禁止は、性的指向や性自認に基づく差別を禁じるものであり、アウティングの禁止は、個人のプライバシーを守るものとして位置づけられています。
共同通信の記事にも「アウティングは重大な人権侵害に当たる」との指摘があります。LGBTs差別の禁止だけでなく、アウティングを禁止する条例の制定も、今後の社会の課題として重要視されています。アウティングの問題は、LGBTsの方々だけでなく、すべての人々の人権を守るための取り組みとして、広く社会に認識されるべきものです。
法律とアウティング
アウティングの問題は、近年の法律の中でも取り上げられるようになってきました。しかし、全ての法律でアウティングの禁止が明文化されているわけではありません。
例えば、今年6月に成立したLGBT理解増進法では、アウティングの禁止に関する明確な記述は存在しません。しかし、2020年に施行されたパワハラ防止法の中では、SOGIハラ(性的指向や性自認に基づくハラスメント)およびアウティングがパワハラの一類型として規定されています。これにより、職場におけるアウティングは法的に禁止されています。
また、アウティングが原因での労災認定の事例も明らかになってきました。これは、アウティングが職場での精神的な負担やストレスを引き起こすこと、そしてそれが重大な健康被害をもたらす可能性があることを示しています。
これらの法律や事例を通じて、アウティングの問題が社会的にどれほど深刻であるかが浮き彫りにされています。法律の枠組みの中でアウティングの禁止を明確にし、実際の取り組みを進めることが、今後の課題として求められています。
今後の期待と展望

アウティング禁止条例の制定やLGBTsに関する法律の整備は、日本社会における大きな一歩と言えるでしょう。しかし、まだまだ取り組むべき課題は多いです。
アウティングの問題に対する認識が広まる中、今後は更なる条例化が進むことが期待されます。特に、まだアウティング禁止条例を持たない自治体において、条例の制定を進める動きが求められています。また、既存の条例を持つ自治体でも、その内容の見直しや強化を行うことが必要となるでしょう。
共同通信の記事にもあるように、「アウティングは重大な人権侵害に当たる」との認識が広まってきています。この認識を基に、LGBTs差別の禁止だけでなく、アウティングを禁止する条例の制定や法律の整備が進められることを強く期待しています。
また、社会全体として、アウティングの問題に対する理解を深める教育や啓発活動も重要です。学校教育や職場研修などを通じて、アウティングの問題についての正確な知識を広める取り組みが求められています。
最後に、アウティングの問題を乗り越え、多様性を尊重する社会を築くためには、私たち一人一人の意識や行動が大切です。私たちが日常の中でできること、それは、相手のプライバシーを尊重し、多様性を受け入れること。このような小さな行動が、大きな変化を生むきっかけとなることを信じています。
参考記事: