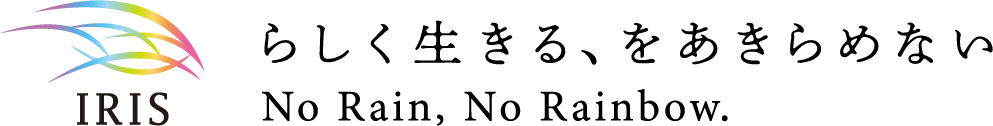IRISがお届けする新連載「Living Voice」。当事者の方々が何らかの活動や団体を運営する中で、どのような想いを持ち、どんな価値観を大切にしているのか。その声に耳を傾けていく企画です。
第1回は、2006年に川崎市を拠点として設立されたゲイ吹奏楽団「音響侍」を取材しました。現在70名を超えるメンバーを抱え、年2回の演奏会を中心に活動を続ける彼ら。団長の高橋さん、執行部の鈴木さんに話を聞くと、そこには「吹奏楽団である前に、ゲイサークルである」という明確な哲学がありました。
音楽の技術よりも、居場所であることを優先する。一見矛盾するようなこの価値観は、どのように生まれ、どう受け継がれてきたのか。20年近い歴史の中で見えてきた、コミュニティを持続させる本質に迫ります。
※発言者名は敬称を省かせていただいております。
高橋さん、鈴木さんのそれぞれの音楽人生について

▶団長の高橋さん、執行部の鈴木さん
取材に応じてくれたのは、団長(運営幹部)の高橋さんと執行部の鈴木さん。2人とも長い音楽キャリアを持つ。
高橋さんは小学6年生から楽器を始め、中学、高校、大学とずっと金管楽器を続けてきた。現在の専門はトランペット。
高橋 「小学校の時、音楽の授業が嫌いだったんです。声変わりも早くて、音楽の授業がすごい苦痛で。でも、小学5年に上がる時に転校して、そこで仲いい友達が器楽クラブに入っていて。その演奏会を聞きに行ったのをきっかけに、自分もやってみたいなと思ったんですよね。嫌いだったはずの音楽なんですけど、そこからのめり込んでいきました。」
友達が演奏する姿を見て「かっこいい」と感じた原体験。そして自分で演奏してみたときの、聴く側とは違う楽しさや達成感。それが高橋さんを今まで音楽に向かわせてきた。
高橋 「トランペットは目立ちますし、ソロを吹く機会も多い楽器なんですよね。うまくはまればとても気持ちいいですし、すごく達成感を味わえる。それと同時に、やっぱりプレッシャーもある。本番が近づくとどんどんプレッシャーで吹けなくなっていくみたいな。でも、うまくいくと、やっぱ気持ちいいですね。」
一方、鈴木さんは高校から吹奏楽を始めた。両親がオーケストラで出会った音楽一家に育ち、父はホルン、母はビオラを演奏していた。
鈴木 「子供の頃から楽器が身近だったんだと思います。中学の時は吹奏楽部の前まで行ってみたんですけど、女子がとても多くて、その集団に馴染めるイメージが湧かなくてやめました。でも高校は工業高校に行ったので、そもそも女子生徒が少なくて、吹奏楽部も3学年で20人ぐらい、ほとんど男子だったので、ここだったらやれるかもと思って始めました。」
鈴木さんの楽器はクラリネット。吹奏楽においてクラリネットは人数が多いパートで、「1人あたりの責任が重すぎない」のも魅力だという。
鈴木 「トランペットと違って1本で目立つっていう機会は少ないんですけど、逆にそれが気楽なのかもしれません。一方で、アンサンブルの時は責任が軽いということはなくて。自分でどうにかできるかできないかギリギリぐらいの難易度で、こういう風に演奏したいなってことを色々考えながらどうにか発表できた時、それが達成感に繋がります。」
興味深いのは、鈴木さんが音楽を続けてきた理由だ。
鈴木 「実は、音楽がとても好きで感動したっていうエピソードは、あんまりないんです。中学の時は卓球部で全くうまくならなかったんですけど、楽器はそこそこできたので、楽しかった。楽器が吹けると、部活動の中でも自信が持てるようになったので、人と喋りやすくなったし、人間的にちょっと自信がついた。」
鈴木 「楽器を続けることによって自分に自信がついて、人とコミュニケーションをとったり仲間に入ったりする、そういうツールにもなったので、それで続けてるんだと思います。」
音楽への情熱だけでなく、「コミュニティに入るためのツール」としての音楽。この感覚は、後に鈴木さんが音響侍に入団する理由とも重なっていく。
ゲイで吹奏楽団をやりたい!から始まった音響侍
▶皆さん真剣に練習に取り組まれています
――まず、音響侍がどのように始まったのか教えてください。
高橋 「実は我々2人とも立ち上げのメンバーではないんです。今から20年ぐらい前、2006年に川崎市を活動拠点とするゲイの吹奏楽団として設立されました。当時は、ゲイの吹奏楽団って関東でも2~3団体ぐらいしかなかったので、今よりは珍しい存在でした。運営の中心のメンバーも色々入れ替わりながら、現在まで活動してきてます。私たちも途中から参加をして、いつの間にか運営に携わるようになったという感じです。」
鈴木 「私は2年目、2007年から参加しています。」
――立ち上げ時、どんなビジョンを持って始まったのでしょうか。
高橋 「ゲイのみんなで集まって一緒に音楽したいなみたいな気持ちは少なからずあったのだと思います。それに賛同した人たちが集まって立ち上がったんだろうなと。」
鈴木 「ゲイで吹奏楽団やりたいっていう、割とシンプルにそんな感じだったんでしょうね。私はその第1回演奏会を見て入団したんですけど、感じとしては、ゲイの吹奏楽団を新しく作ろうとか、そういった温度感だったなという印象です。当時はそのようなコンセプトの団体自体まだあまり多くなかったので。」
壮大な社会的メッセージがあるわけではない。ただ「一緒に音楽をしたい」というシンプルな想いから始まった音響侍。しかし、20年近く経った今、彼らが大切にしている価値観は、実は設立当初から一貫していたのかもしれない。
入団のきっかけは「ここで一緒にやりたい」
▶飲み会など盛んにおこなわれているようです
鈴木さんが音響侍に入団したきっかけは、多くの人が想像するものとは少し違っていた。
鈴木 「私は演奏会を聞いて入団したんですけど、音楽も楽しめそうだし、それよりもこのコミュニティに入りたかったんですよね。」
――音楽よりも、コミュニティに入りたかった。
鈴木 「2006年当時はスマートフォンがまだない時期で、ガラケーの時代だったんです。今ほど人と出会うことは簡単ではなかった。それに1対1で会うのも面倒じゃないですか。とりあえず、どっかのサークルにポンって入ったら、知り合いが増えやすいだろうと。そして、せっかくだから今までやってきた楽器を活かせる団体だったら、一挙両得でいいんじゃないかみたいな気持ちでした。」
一方、高橋さんはmixiで検索して音響侍を見つけ、見学に行った。
高橋 「なんか楽しかったんですよね。同じセクシュアリティの方々に囲まれて、可愛がられて、一緒に楽器吹いて、飲み会とか行って、その雰囲気がすごく楽しかったので、ここで一緒にやりたいなという風に思ったのがきっかけです。」
音楽の技術レベルでもなく、演奏会の完成度でもなく、「雰囲気」が決め手だった。この感覚は、後に音響侍が大切にしていく価値観の原点とも言える。
「吹奏楽団である前に、ゲイサークルである」
▶演劇パートの練習風景、音響侍の名物です
現在、音響侍は年2回の定期演奏会を中心に、毎週日曜日の練習、LGBTs系音楽イベントへの参加、合宿や花見、バーベキューなどの親睦イベントを開催している。メンバーは70名を超える。
この活動の根底にある哲学を、高橋さんはこう語る。
高橋 「僕ら運営してるメンバーが思っていることは、音響侍は吹奏楽団である前に、ゲイサークルであり、同じセクシュアリティを持ってる人が集まっているコミュニティだと考えています。その中での日々の活動がほかの趣味と比べても楽しいって思えることが、この楽団に所属する大きなモチベーションの1つなのかなって思っています。」
高橋 「楽しくないとね。社会人で、時間もお金も限られる中で、わざわざやってる活動ですから。実際にみんな練習には来れる範囲で来てくれていたり、練習ない日もわざわざ会ってたりとかして。そういう様を見ていると、それぞれの居場所として機能してるのかなと実感しています。」
フラットな組織が生み出す自由で活発な活動
鈴木 「音響侍は誰が偉いわけでも、誰かが強権的に決めるわけでもなくて、運営側としてはその環境を整えるけども、基本的には所属してるみんなのやりたいことが自然とやれるような環境になればいいかなと思っています。」
高橋 「確かに結構フラットなんですよね。楽団のメンバーがみんな運営してる。音楽的な面、日々の練習とかを仕切ってくれる団員もいますし、我々みたいに運営やってる人間もいますけど、それでも団員と割とフラットでいようとしている。みんな好き勝手言いながら、お互いに思ったり気づいたことが、言いやすい雰囲気ではやっていきたいなって思いますね。」
この哲学を体現する象徴的な出来事が、2年前に行われた「プロデューサー公募企画」だった。
鈴木 「演奏会をまるごとメンバーにプロデュースしてもらおう、みたいな企画をやったことがあって。演奏する曲目だけではなく、どういうコンセプトや演出で演奏会をやるのか、丸ごと企画から公募するってのをやったんです。」
鈴木 「企画を出してくれたメンバーは4~5名でした。企画者がみんなの前でプレゼンして。オンラインだったのでコメント欄で盛り上がったり、コンペ自体がひとつのイベントみたいな雰囲気になりました。」
鈴木 「その中で一番人気だった企画をやることになりまして。結果的にその企画はお客様アンケートも好評でしたし、メンバーの満足度も高かった。」
鈴木 「完全にボトムアップだったんですけど、みんなで参加してる意識があった方が、自分たちで楽団を作ってるんだという効力感にもつながります。自分たちでどんなことやったら楽しいんだろうってことを考えるきっかけになり、能動的にメンバーが活動できる仕組みができたという感触がありました。」
トップダウンではなく、ボトムアップ。指示待ちではなく、自主性。音響侍が目指すのは、部活文化とは真逆の、フラットで自由なコミュニティだった。
演奏が上手い、以外の評価軸がある楽団
▶アイドルのダンスも披露、本当に楽しそうです(笑)
高橋 「音響侍としては、音楽以外、例えばダンスですとか、お芝居とか、吹奏楽の演奏以外のところにも力を入れているのが特徴の1つなんです。他の団体さんは演奏だけを真面目にやられることが多いんですけど、音響侍は演奏以外のところも力を入れてやっています。そういった企画とか演出も、自分たちで考えて作っていけるような形にしています。」
高橋 「基本的には自分たちで考えて、自分たちで作って、出たい人が出て、演奏もやって、できればみんなで頑張って、終わった後のその達成感みたいなのもみんなで分かち合いたい、そんな気持ちです。それをまた次の活動の原動力にしてもらうというのは、個人的には大事にしてるポイントですね。」
鈴木 「基本的に人間は居場所がないと生きられないと思ってるんですよね。居場所が職場にある人は別にいいんですけど、おそらくセクシュアルマイノリティの人は職場が居場所になりづらい傾向にあると思う。なので、仕事以外で居場所となるところがあるといいと思います。」
鈴木 「そして、それが音楽サークルだったとしても、音楽だけを頑張ろうという雰囲気ではなく、音楽もやってるけど、音楽以外の評価軸もあるサークルが存在するのは、価値あることだと思ってやってますね。」
楽器が上手でなくても、ソロが吹けなくても。逆にダンスができても、お芝居ができても、企画が得意でも。音響侍には、音楽だけではない多様な評価軸がある。それが、多くの人にとっての「居場所」を可能にしている。
「青いこと」を恐れない文化が世代をつなぐ
▶仲の良さがこの上なく伝わってきます
音響侍には、長く活動を続けてきた中で培われた独特の雰囲気がある。お二人はそれを「青さ」という言葉で表現した。
鈴木 「私たちの楽団って、やってることが若いというか、青いんですよね、基本的に。青いことをやり続けることを楽しめるという、その考え方に違和感なく共感できる人たちが集まっている。だから、そんな大きく価値観がずれないと思うんです。」
ここで言う「青いこと」とは何か。それは、ダンスやお芝居といった演出面での冒険だけではない。完璧さよりも楽しさを優先すること、トップダウンではなくボトムアップで企画を作ること、音楽の技術以外の評価軸を大切にすること――そうした、ある種の「形に捕らわれすぎない」姿勢全体を指している。
この「青さ」を許容し、むしろ大切にする文化があるからこそ、世代が変わっても音響侍らしさが保たれている。大人になっても「青臭い」ことを恥じない。その覚悟が、コミュニティの一貫性を生んでいるのだ。
高橋 「来年、ちょうど創立から20周年を迎えます。これからも常に変化を恐れない、少しずつでも変化し続けられる集まりであれたらいいかなと思ってます。」
高橋 「当然今みたいな大きなイベントもやって、それ自体に変化をもたらすという側面もあります。同時に、自分たちも社会の変化を受ける立場でもあり、何かのきっかけで時代が変わったりとか、僕らの価値観や環境が変わる出来事もやっぱりあって。」
高橋 「10年前、20年前とか振り返っても、あの頃はガラケーが主流だったなとか、今当たり前のものが、あの当時は当たり前じゃなかったりとかっていうことが当然あるので、きっとそれってこれからも起こると思うんです。」
高橋 「その変化に合わせて、音響侍も少しずつでも変化していかないといけないと思いますし、きっと自然に変わっていくものであるとも思います。ですから、あまり固くならずに柔軟にコミュニティの形を変えていくのが、長く続いていく秘訣なのかなと思います。」
「青さ」を大事にし、変化を恐れず、メンバー主導で作り上げていく。この3つの要素が、音響侍を20年間支えてきた土台だった。
2人にとっての音響侍は「大切な仲間と出会える場所」
▶毎回、数百人のお客さんが聞きに来られます
インタビューの最後、2人に音響侍とはどんな存在かを尋ねた。
高橋 「自分の人生の時間をかなり音響侍に費やしてきています。この楽団を構成しているメンバーのみんなが、大切な仲間であり、友人であり、家族であり。一言で言うと、自分にとって大切な居場所なんでしょうね。」
鈴木 「仲間と出会える場所です。私だけじゃなくて、多くの人にとっての居場所であり、そこに行けば仲間がいる場所。そして、音楽もやっているけど、音楽以外の評価軸もあるところ。そういう価値のある場所です。」
一歩踏み出せないが、これから音響侍吹奏楽団に入りたいと思っている人へのメッセージを聞くと、2人の言葉は明快だった。
高橋 「今までお話ししたような価値観だったりとか、音響侍の楽しみ方がご自身に合うようであれば、ぜひ気軽に遊びにいらしていただけたらと思います。楽器が吹ける吹けないは基本的に問うてないですから。」
鈴木 「音響侍は基本的には吹奏楽団です。でも、演奏会の中では変なことも色々やってるので、逆にそれがちょっとハードル高く見えることもあるみたいです。でも、基本的にダンスとか演劇とか、全員がやってるわけじゃなくて、演奏だけというメンバーの方が多いです。ただ、そういうことをやってる雰囲気の中に入りたいなと思ってくださるのであれば、おそらく楽しめると思いますので、是非お問い合わせいただけると嬉しいです。」
編集後記
音響侍吹奏楽団のインタビューで最も印象的だったのは、「音楽を第一目的としない」という言葉だった。音楽団体でありながら、音楽よりも大切にしているものがある。それは「居場所」であり、「コミュニティ」であり、「仲間」だった。
技術を追求するゲイの音楽団体は今や多数ある。でも、技術以外の評価軸を持ち、それを明確に打ち出している団体は意外と少ない。
音響侍は、音楽という共通言語を持ちながらも、それ以上に「人がつながる場所」であることを選択した。
20年間、メンバーは入れ替わり、時代も変わった。ガラケーからスマートフォンへ、出会い方も変化した。でも変わらないものがある。それは「ここは、仲間と出会える場所」という、シンプルで力強い信念だ。
それは、コミュニティの本質が何であるかを、明確に示している。
音響侍が20年間実践してきたこの価値観は、他の多くの当事者サークルにとっても示唆に富むものだろう。
「Living Voice」第1回は、音楽を通じて「居場所」を創り続ける人々の物語だった。次回も、当事者が運営する様々な活動の現場から、その想いと価値観を伝えていく。
取材・文:IRIS Times編集部
協力:音響侍吹奏楽団
音響侍吹奏楽団への問い合わせや見学希望については、以下お問い合わせ先からご連絡ください。
音響侍吹奏楽団 公式ウェブサイト
https://onkyo-smri.sakura.ne.jp/
公式X
https://x.com/onkyo_samurai
公式Instagram
https://www.instagram.com/onkyo.samurai