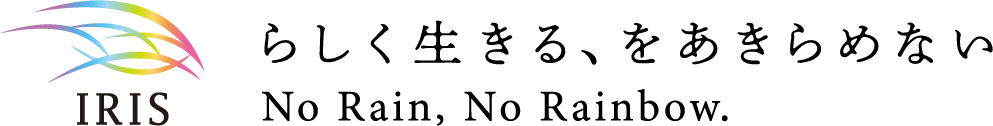日本ではゲイカップルをはじめとする同性カップルの婚姻が法的に認められておらず、G7で唯一同性婚制度がない国となっています。一方で、2025年1月にはタイが東南アジア初の同性婚合法化を実現し、世界では38カ国が同性婚を法制化済みです。
日本国内では司法による違憲判断が相次ぎ、パートナーシップ制度の人口カバー率が90%を超えるなど、社会的な理解は着実に進んでいます。世論調査では66%が同性婚に賛成しており、企業からの支持も拡大しています。
本記事では、ゲイ・同性婚を巡る日本の現状と世界の最新動向、実現への課題について詳しく解説します。
※当方IRISではLGBT以外のセクシュアルマイノリティも包括するという意味でLGBTsを掲げておりますが、本記事では分かりやすさを重視する為、LGBT、LGBTQ+として紹介していきます。
同性婚とは何か:基本的な理解
同性婚とは、法律上の性別が同じ二人(男性と男性、女性と女性)が結婚することを指します。2025年の時点で、総人口15億人(世界人口の20%)を有する38ヶ国で同性カップルの結婚が合法的に行われ認められています。最新で同性結婚を合法化した国は、タイ王国です。
同性婚が認められると、結婚した二人は異性婚カップルと同じように、相続権、扶養控除、医療同意権などの法的な権利を得ることができます。多くの場合、性別のカテゴリーが同じ者同士が男女の夫婦のように家族としての親密さを基礎として、社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、維持することを指します。
法域によって異なりますが、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な権利が付与され、法的な保障や保護が行われる制度となっています。同性婚は、従来から異性同士に認められてきた法的な意味での結婚(婚姻)を指すことが多く、法的な効力を持つ制度として位置づけられています。
世界における同性婚の現状と最新動向
世界全体では同性婚の合法化が着実に進んでいます。2001年4月1日にオランダが世界で初めて法制化して以降、2025年1月23日のタイ王国の合法化により、38ヶ国で同性結婚が法制化されています。
現在、同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を持つ国・地域は世界中の約22%の国・地域に及んでいます。
世界の同性婚合法化の流れ
世界で最初に同性婚が認められた国々を時系列で見ると、2001年のオランダを皮切りに、2003年ベルギー、2005年スペイン・カナダ、2006年南アフリカ、2015年アメリカ(全州で合法化)、2019年台湾(アジア初)、2025年タイ(東南アジア初)となっています。
同性婚かパートナーシップ制度のいずれかを持つ国や地域のGDPは、世界全体のおよそ58%を占めており、経済発展と多様性の受容には密接な関係があることが示されています。先進国を中心に、人権重視の観点から同性婚の法制化が進んでいる状況です。
G7諸国においては、日本以外のすべての国が同性婚もしくは同等の制度を導入済みとなっています。
2025年の重要な動向:タイの同性婚合法化
2025年1月23日、タイで東南アジア初となる同性婚を合法化する「結婚平等法」が施行されました。同性カップルが一斉に婚姻届を提出するイベントが行われ、1400組以上が婚姻届の提出を目指しました。タイの官報は前年9月24日、同性婚を認める「結婚平等法」をワチラロンコン国王が承認し、公布したと発表していました。
タイの法改正では、「男性」や「女性」を「個人」と表現し、性別に関係なく結婚できるようになりました。同性同士でも配偶者への治療の同意書に署名したり、相続を受けたりする権利を得られるようになります。バンコクの高級ショッピングモールでは集団結婚式が行われ、200組以上のカップルが誓いを立てるために列を作りました。白いドレスやタイの伝統衣装など、さまざまな衣装で参加するカップルが見られました。
日本における同性婚の現状
日本では2025年現在、同性婚は法的に認められていません。イタリアが2016年に同性カップルに対するシビル・ユニオンを導入したことで、日本はG7で唯一国レベルの「同性カップルに関する国の法律」がない国となっています。
法的な現状と制度的課題
日本では現在、結婚は男女間でのみ認められています。同性のカップルは、法律上の夫婦になることができません。
結婚に関する法律は民法で定められています。民法では結婚の条件として性別について明確に書かれてはいませんが、条文の中で「夫婦」という言葉が繰り返し使われるなど、男女の結婚を前提とした表現になっています。特に民法第739条第1項などの規定から、「民法は同性婚を認めていない」と解釈されているのが現状です。
同性婚を法的に認められるかどうかは、日本国憲法第24条をどう解釈するかで議論が分かれています。憲法第24条第1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と書かれています。この条文の「両性」という言葉をどう解釈するかで、憲法改正が必要かどうかという議論に分かれています。
憲法改正が必要だとする考え方では、「両性」という言葉は男女を指しており、同性婚を認めるためには憲法を改正する必要があるとしています。
憲法改正は必要ないとする考え方では、憲法第24条第1項は、もともと家族形成の自由を保障し、婚姻における男女の平等を確立し、家や親の意向ではなく結婚する本人たちの意思を尊重することを目的として作られたものだと主張しています。つまり、この条文は同性婚を禁止することが目的ではなく、個人の自由と平等を守ることが目的だったのだから、現在の憲法のままでも同性婚は認められるべきだという考え方です。
世論の変化と支持状況
2023年2月に日本テレビが行った世論調査によれば、同性婚に賛成と答えた割合は全体で66%となっています。
年代別の支持状況は以下の通りです。
- 10・20代:87%が賛成
- 30代~60代:賛成が多数を占める
- 70代:賛成40%・反対44%で拮抗
幅広い世代で同性婚に賛成する割合が多いことが分かります。
注目すべき点として、党として同性婚に後ろ向きな態度をとる自民党ですが、自民党支持層の半数以上(54%)が同性婚に賛成しているという調査結果があります。政党支持と個人の価値観が必ずしも一致していないことを示しており、世論の変化を表しています。
国際的な調査では、調査対象となった30カ国を平均すると、56%が「同性カップルの合法的な結婚を認めるべき」と答えており、日本は38%が「認めるべき」と回答し、9%が「認めるべきではない」と回答しています。
関連記事:
同性婚をめぐる裁判の動向
日本では2019年以降、同性婚の合憲性を正面から問う集団訴訟が全国5地方裁判所で提起され、司法による画期的な判断が相次いでいます。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟
同性婚の合憲性を正面から問う集団訴訟が2019年2月と9月に東京、大阪、札幌、名古屋、福岡の5つの地方裁判所で提起されました。
法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できないため、以下の日程で提訴が行われました:
- 2019年2月14日:札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で一斉提訴
- 2019年9月5日:福岡地裁でも提訴
現在までの地方裁判所判決の状況は以下の通りです。
| 裁判所 | 判決時期 | 判断 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 札幌地裁 | 2021年3月 | 違憲 | 初の違憲判決(憲法14条1項違反) |
| 名古屋地裁 | 2023年5月30日 | 違憲 | 憲法24条2項および14条1項違反 |
| 東京地裁(一次) | 2022年11月30日 | 違憲状態 | 憲法24条2項違反状態 |
| 東京地裁(二次) | 2024年3月 | 違憲状態 | - |
| 福岡地裁 | 2023年6月8日 | 違憲状態 | 憲法24条2項違反状態 |
| 大阪地裁 | (詳細不明) | 合憲 | 将来の違憲可能性を示唆 |
9つの判決(地裁6件、高裁3件)のうち、同性婚ができない現在の法律を合憲だと判断したのは大阪地裁の判決のみです。その大阪地裁判決においても、国が立法しないことが将来的に憲法24条2項に違反するものとして違憲になる可能性を示しています。
高等裁判所での画期的判決
2025年1月31日時点で、6つの地裁判決と3つの高裁判決(札幌、東京一次、福岡)が出されています。
札幌高等裁判所(2024年3月14日)
同性間の結婚を認めていない民法と戸籍法の規定は「憲法24条1項、同2項、14条に違反する」との判断を下しました。同性婚に関する日本初の高裁判決として、憲法24条1項についての違憲判決は初めてとなり、画期的な判決となりました。
東京高等裁判所(2024年10月30日)
東京高裁(谷口園恵裁判長)は、「合理的な根拠に基づかない差別的な取り扱いだ」と認め、規定は憲法に違反すると判断しました。「個人の尊厳と両性の平等に立脚した立法」を求める憲法24条2項と「法の下の平等」を定めた14条に違反すると指摘されました。
福岡高等裁判所(2024年12月13日)
現時点で最も新しい判決となった福岡高裁判決では、婚姻制度の対象から同性カップルが除外されている現在の法律は、幸福追求権を保障する憲法13条に反すると判断した点で注目を集めました。
現在、札幌、東京一次、福岡高裁判決については上告審に係属中で、最高裁判決も近づいています。2025年3月には、名古屋高裁、大阪高裁でも判決言渡し予定となっており、司法による同性婚への理解がさらに進展する可能性があります。
パートナーシップ制度の広がり
同性婚が法制化されていない日本では、自治体独自のパートナーシップ制度が急速に拡大し、2025年現在、人口カバー率は90%を超えています。
制度の概要と現状
日本国内の各地方自治体が戸籍上同性であるカップルに婚姻に相当する関係にあると認める「パートナーシップ宣誓制度」(パートナーシップ制度)が運用されています。
「パートナーシップ制度」は、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。
日本では2015年に東京都渋谷区議会が初めて「結婚に相当する関係」と認める渋谷区パートナーシップ証明書を出す条例を制定しました(同時期に世田谷区も同性パートナーシップ宣誓を開始)。制度導入以降、急速な拡大を見せており、現在では全国に広がっています。
人口カバー率の拡大
同性婚法制化について、政府はパートナーシップ制度の導入状況も注視と言っていますが、ついに人口カバー率は約90%を超えました。現在の導入状況は以下の通りです。
- 導入自治体数:488以上(2025年3月1日時点)
- 人口カバー率:約90.8%(2025年3月1日時点)
- 都道府県レベルでの導入:33都道府県(過半数を超える)
- パートナー登録件数:7,351組(2024年5月31日時点)
制度導入は急速に拡大しており、2022年6月には219自治体だったのが、2025年3月には488以上の自治体に達し、約3年間で2倍以上に増加しました。パートナーシップ制度には、大きく分けて「渋谷区型」「世田谷区型」の2つがあります。
- 渋谷区型:地方の条例として制定され、法律に近い効力を持ちますが申請や審査が必要
- 世田谷区型:自治体の要綱として制定され、手続きが比較的簡単という特徴
関連記事:
制度の効果と限界
受けられるメリットは以下の通りです。
- 病院で家族と同様の扱いを受けられる
- 公営住宅への入居に家族として入居可能
- 生命保険の受け取りにパートナーを指定することができる
- 民間の家族割などが利用可能
しかし、パートナーシップ制度には重要な限界があります。自治体パートナーシップに登録しても、以下の法的利益は得られません。
- 所得税の配偶者控除
- 健康保険への被扶養者としての加入
- 財産分与や相続
- パートナーの子供の親権
法的な効力がないため、国の制度に関わる部分では依然として課題が残っています。パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力はありません。法的に「家族」とは認められず、例えば残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。
関連記事:
- パートナーシップ制度とは?結婚との違いを解説|何ができる?何ができない?
- 【2022年4月最新】法的効力は?パートナーシップ制度でできること
- 日本の同性婚の現状とパートナーシップ制度との違いについて解説
- パートナーシップ制度でできること、できないことって何?具体的に解説していきます!
ゲイカップルが直面する課題
同性婚が認められていない現状で、ゲイカップルをはじめとする同性カップルが直面する具体的な課題は多岐にわたります。法的な不利益として、以下のような問題があります。
- パートナーの法定相続人になれない
- 税制上の優遇措置を受けられない
- 遺族年金が支給されない
- パートナーの医療同意権がない
婚姻には沢山の法的な権利や事実上の法的保護が紐づいています。婚姻できない同性カップルは法的権利を一切享受できず、具体的な不利益を日々被っているため、不利益の解消が必要です。
社会的な課題としては、家族として認識されないことによる差別や偏見、職場での理解不足、医療現場での家族扱いされない問題などがあります。同性カップルの生活の質に大きな影響を与えており、早急な解決が求められています。
経済的な負担も大きく、相続時の高額な税負担、保険の受取人指定ができない問題、住宅ローンの連帯債務者になれない制約などが挙げられます。
関連記事:
同性婚実現への道筋と課題
日本における同性婚法制化には政治的、社会的、国際的な観点から複数の課題があり、実現には段階的なアプローチが必要とされています。
政治的な動向
日本でも、実は、自民党以外の主要政党は、公明党も含めてほとんどが同性間の婚姻の法制化に賛成しています。日本で同性間の婚姻が法制化できない直接的な理由は、自民党の中に強力な反対勢力が存在するという点にあります。
同性婚の整備に前向きな立憲民主党と社民党は、2023年3月に民法の改正案を衆議院に提出しました。しかし、現在の与党である自民党の姿勢により、法制化への道のりは困難な状況が続いています。
政治的な解決には、世論の更なる高まりと政治家の意識変化が不可欠です。選挙における投票行動も重要な要素となり、より多くの国民が政治により関心を持ち、投票という行動を起こす必要があります。
企業の支持拡大
「Business for Marriage Equality」(同性婚の法制化に賛同する企業を可視化するキャンペーン)に賛同する企業が2025年7月2日時点で639社に達しています。企業による支持の表明は、社会全体の意識変化を促進する重要な要素となっています。
札幌高裁判決では、同性婚の法制化に賛同する企業への言及があり、経済界からの支持も広がっています。
企業には、「世論の高まり」を国会や裁判所が実感できるよう、橋渡しをすることが求められます。無関心は中立ではなく、差別への加担であると指摘されており、企業がアクションを取り、世の中が変わることへの期待が高まっています。
関連記事:パートナーシップ制度、企業はどう対応? 企業の福利厚生は?
国際的な評価と課題
日本におけるLGBTQ+に関する法制度の進み度合いはOECD加盟35カ国中34位と大きく立ち遅れており、国連からも法改正や状況改善の勧告を再三受けてきました。国際的な視点から見ると、日本の取り組みは大幅に遅れている状況です。
G7中、何らの制度も有していないのは日本だけであると指摘もあります。先進国としての責任と国際的な地位を考慮すると、早急な法整備が求められています。
一方で、日本以外のG7諸国では、以下の柱となる法整備が進んでいます:
- LGBT差別禁止法
- 婚姻の平等(同性婚)
- トランスジェンダーの人権を保護する法律
国際社会における日本の評価と信頼性を維持するためにも、同性婚を含む包括的な法整備が急務となっています。
まとめ:同性婚の未来への展望
2024年3月14日の札幌高等裁判所を皮切りに、10月30日の東京高裁、12月13日の福岡高裁と、高等裁判所レベルで3件連続の違憲判決が出されました。特に福岡高裁判決では、憲法13条(幸福追求権)違反も認められ、司法による違憲判断の根拠がさらに拡大しています。
現在(2025年1月31日時点)までに出された9つの判決のうち、合憲判決は大阪地裁のみで、その他はすべて違憲もしくは違憲状態との判断が示されています。現在、札幌、東京一次、福岡の各高裁判決が最高裁に上告中で、最高裁での統一的判断が近づいています。
世界的には38カ国で同性婚が合法化され、特にアジアでは台湾、ネパール、タイが法制化を実現しました。日本においても、世論の6割以上が同性婚に賛成し、パートナーシップ制度の人口カバー率が90%を超えるなど、社会的な理解は着実に進んでいます。
同性婚の法制化は、単に同性カップルの権利保障にとどまらず、多様性を認め合う社会の実現、国際的な信頼向上、経済活性化など、社会全体にとって大きな意義を持つ課題です。
関連記事: