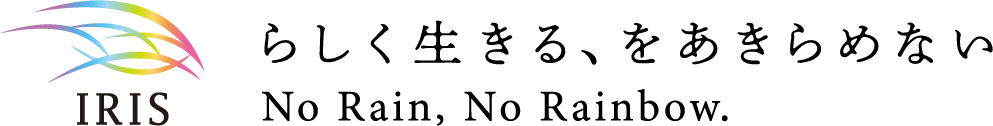先日、厚生労働省より「令和6年度 職場におけるダイバーシティ調査・推進事業 報告書」が公表されました。
- 厚生労働省「令和6年度 職場におけるダイバーシティ調査・推進事業 報告書」
https://www.mhlw.go.jp/content/001511340.pdf
この調査は、性的指向や性自認(SOGI)に関する職場環境の実態や課題を明らかにすることを目的としたもので、全国の企業2,442社、一般労働者3,000名、当事者2,000名を対象に大規模なアンケートが実施されました。さらに、企業・自治体へのヒアリングも行われ、多角的な視点から分析がされています。
企業の7割以上が「SOGIへの理解促進の必要性」を認識している一方で、具体的な制度整備や相談体制の導入はごく一部にとどまっており、いわば「意識と行動のギャップ」が浮き彫りになっています。また、SOGI当事者の約6割が「職場でカミングアウトに不安を感じている」と回答しており、偏見や無理解が今も深刻な心理的バリアとなっていることが明らかになりました。
このような状況にあることはIRISも認識している部分で、「不動産業界×LGBTQ+」をテーマにIRISも協力する以下のイベントを実施予定です。

「理解はしてるけど、実際には...」企業の本音が見えてくる
みんな、気持ちはあるということが分かった
実際にデータを深く掘って見てみましょう。
まず驚いたのは、企業の意識の高さです。「性的マイノリティが働きやすい職場環境をつくるべき」と答えた企業は実に78.5%。特に中小企業(99人以下)では、5年前の66.8%から77.2%へと大幅にアップしています。
「時代の流れかな」「人権意識が高まったよね」そんな声が聞こえてきそうです。
でも、実際にやってるかというと...
ところが、です。実際に性的マイノリティに配慮した取組を実施している企業は、なんとわずか10.4%。約8割の企業が「やるべきだ」と思いながらも、実際の行動には移せていないという現実があります。
これって、ダイエットを「やらなきゃ」と思いながらなかなか始められない私たちの心境と似ているかもしれませんね。気持ちはあるけれど、「何から始めればいいの?」「本当に効果あるの?」と躊躇してしまう。
大企業と中小企業、その差は歴然
規模で見える格差の現実
取組実施率を企業規模別に見ると、まるで階段のような差が現れます:
- 1,000人以上の企業: 43.1%
- 300~999人: 18.5%
- 100~299人: 12.1%
- 99人以下: 7.0%
この数字を見て、思わず「やっぱりね...」とため息をついた中小企業の人事担当者も多いのではないでしょうか。
大企業なら専門部署もあるし、予算もある。でも中小企業は「そんな余裕ないよ」というのが正直なところ。日本の企業の99.7%が中小企業であることを考えると、この格差は深刻な社会問題といえそうです。
なぜこんなに差がつくのか
大企業の人事部長さんに話を聞くと、「まず専任担当者を置けるかどうかが大きい」と言います。一方、従業員50人の会社の社長さんは「やりたい気持ちはあるけど、何をどうすればいいのか分からない。相談する相手もいないし...」と困り顔。
この温度差、なんとかならないものでしょうか。
見えてきた当事者たち、でも新たな心配も
カミングアウトする勇気の増加
嬉しいニュースもあります。社内に性的マイノリティ当事者がいることを「認知している」企業が増えているんです。特に大企業では40.6%にも達しています。
認知のきっかけで最も多いのは「当事者からのカミングアウト」(26.9%)。つまり、職場で自分らしさを表現する勇気を持つ人が増えているということです。
でも、情報管理は大丈夫?
ただし、ここで新たな心配が生まれます。カミングアウトが増えるということは、その情報が適切に管理されているかが重要になってくるということ。
実際に相談窓口を設置している企業でも、「これまでに相談があったことはない」が50.5%。これは相談しにくい環境なのか、それとも窓口の存在が知られていないのか。当事者の方々の心境を思うと、複雑な気持ちになります。
ハラスメント対策、実はまだまだ遅れてる
一般的なパワハラ対策との大きな差
ちょっとショックだったデータがこれです。性的指向や性自認に関わるハラスメント防止の取組実施率は71.8%。一方、一般的なパワーハラスメント対策は**95.2%**の企業が実施しています。
20ポイント以上の差って、結構大きいですよね。
実際に起きているハラスメント
労働者調査では、こんな声が聞こえてきます:
- 「容姿や外見についてしつこく言われる」(26.3%)
- 「『男らしく』『女らしく』を強要される」(19.1%)
- 「性的マイノリティをネタにした冗談を聞かされる」(7.6%)
これらの数字の背後には、リアルに傷ついている人たちがいることを忘れてはいけませんね。
企業の本音:「やりたいけど、どうすれば?」
企業が抱える素朴な疑問
取組を進めたい企業が直面している課題を見ると、なんだか親近感がわきます:
- 当事者のニーズがわからない(35.5%)
- 社員の関心が低い(30.6%)
- 何をすればいいかわからない(27.8%)
- 詳しい人がいない(26.5%)
「当事者の声を聞きたいけど、どう聞けばいいの?」「研修やりたいけど、何を教えればいいの?」そんな素朴な疑問が聞こえてきそうです。
「いない」のか「見えない」のか
取組をしていない理由として「社内に性的マイノリティ当事者がいないため」と答えた企業が54.0%。でも統計的には約8-10%の人が性的マイノリティとされています。
つまり、「いない」のではなく「見えない」だけかもしれません。見えない理由を考えると、やっぱり職場環境の整備が必要だということになりますね。
これからどうする?未来への道筋
差別されないこと、選べること。それは“特別”ではなく、当然の権利。
私たちIRISは、LGBTQ+をはじめとする多様な人々が安心して「住まい」を選べる社会の実現を目指し、不動産領域から社会課題に取り組んでいます。
けれど、住まいと職場の課題は決して切り離せるものではありません。
たとえば、
「職場でカミングアウトしていないから、住宅手当を受けにくい」
「家族にカミングアウトしていないため、保証人や緊急連絡先を設定しづらい」
「社宅扱いで借りる物件の管理会社が“悪意なく”アウティングしないか不安」
こうした声は、私たちが日々出会っている当事者のリアルです。
職場における差別や沈黙の強要は、住まいにも、そして人生そのものにも深く影響を及ぼします。
「やり方がわからない」という壁を超えるために
今回の報告書が大きな意義を持つのは、現実を可視化しただけでなく、企業や自治体による具体的な好事例(18事例)を紹介している点です。
SOGIに配慮した相談窓口の設置、管理職向け研修の実施、ユニバーサルな就業規則の整備など、規模や業種を問わずすぐに参考にできる取り組みが数多く掲載されています。
私たちIRISも、「不動産業界×SOGI」の領域において、企業から「何から始めたらよいかわからない」という声をたびたび耳にしてきました。
だからこそ、こうした“事例の見える化”や“正しい情報の流通”は非常に重要だと考えています。
「選べる」と感じられる社会へ
報告書は、制度の整備だけでなく、職場や社会における「信頼」の醸成もまた、不可欠であると伝えています。
選択肢が“ある”ことと、選べると“感じられる”ことには、大きな違いがあります。
本質的なダイバーシティとは、「安心して選べる社会」であり、そのためには制度と空気、両方のアップデートが必要です。
IRISもその一歩を進めていきます
私たちIRISでは先日立ち上げた一般社団法人住宅みらい会議を通じて、LGBTQ+当事者の住宅課題に特化したシンポジウム「LGBTQ+を取り巻く住宅市場最前線!~調査結果からわかる当事者対応の課題とその解決策~」の開催、企業向けのダイバーシティ研修、自治体との連携事業などを進めています。
“選べる社会”を、ただの理想論で終わらせないために。
そして何より、一人でも多くの「声なき声」が、社会の真ん中に届くように。
これからも、現場と制度をつなぐ挑戦を続けてまいります!