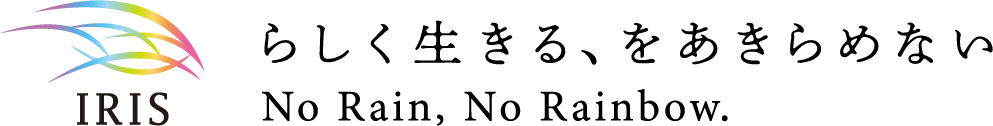近年、企業や自治体でよく耳にするようになった「アライ」という言葉をご存知でしょうか。
アライとは、LGBTQ+をはじめとする性的マイノリティの人々を理解し支援する人を指す概念で、多様性を受け入れる社会づくりの重要な担い手として注目されています。
SNSでアライを表明する人が増え、職場での研修も活発化する中、アライの正確な意味や具体的な活動内容について詳しく知りたい方も多いでしょう。
本記事では、アライの基本的な定義から歴史、具体的な支援方法まで、包括的に解説いたします。
※当方IRISではLGBT以外のセクシュアルマイノリティも包括するという意味でLGBTsを掲げておりますが、本記事では分かりやすさを重視する為、LGBT、LGBTQ+として紹介していきます。
アライとは何か?基本的な意味と定義
アライ(Ally)とは、英語で「同盟」や「支援」を意味する言葉が語源となっており、LGBTQ+をはじめとする性的マイノリティの人々を理解し支援する考え方、またはそうした立場を明確にしている人々を指します。
アライ本人は必ずしも性的マイノリティではありませんが、偏見や差別をなくし、多様性を受け入れる社会の実現を目指して活動しています。近年では、SNSのプロフィールに「アライ」と記載するなど、支援の意思を表明する人が徐々に増加しており、日本企業や自治体でもアライを増やす取り組みが活発化しています。
アライになるために特別な資格や認定は必要なく、誰でも表明できる敷居の低い概念として広がっています。
関連記事:アライ(Ally)とはLGBTにとって大きな存在。アライになる方法や活動内容の紹介!
アライの発音と読み方
アライ(Ally)の正しい発音は「アラァイ」で、「ア」または「ラ」にアクセントを置きます。日本語の「洗い」や「新井」とは異なり、「イ」にアクセントがない点に注意が必要です。
英語の発音記号では「əlɑɪ」と表記され、舌先を前歯の裏につけて「ウ」と「ル」を同時に言うつもりで短く「ア」につなげ、最後に「エ」と「イ」を同時に発音するイメージです。
カタカナ表記では「アライ」が一般的ですが、より正確には「アラァイ」に近い音になります。日本でも徐々に認知度が高まっており、正しい発音で使用することで、より適切なコミュニケーションが可能になります。
アライの歴史と語源
アライという概念がどのように生まれ、現在まで発展してきたのかを理解することは、その意義を深く知る上で重要です。アライの歴史は約35年前のアメリカの教育現場から始まり、世界中に広がっていきました。
1988年アメリカから始まった運動
アライの起源は1988年にアメリカの高校で、ストレート(異性愛者)の生徒によって作られた「ゲイ・ストレート・アライアンス(GSA)」というクラブにあると言われています。
同性愛者への嫌悪や偏見の解消を促進する彼らの活動は「ストレートアライアンス」と呼ばれ、徐々に全米に広がっていきました。当初はストレートの人々がLGBTQ+当事者を支援するという意味で使われていましたが、現在では性的指向や性自認に関わらず、お互いを理解し支援し合う概念として発展しています。
英単語「ally」の語源はラテン語の「alligare」で、「結びつける」という意味を持ちます。現代におけるアライの概念も、異なるセクシュアリティの人々を結びつけ、共に歩む存在としての意味が込められています。
LGBTQとアライの関係性
アライが支援するLGBTQ+とは具体的にどのような人々なのでしょうか。また、なぜアライによる支援が重要なのでしょうか。ここでは、LGBTQ+の基本的な知識とアライとの関係について詳しく解説します。
LGBTQとは何か
LGBTQは「レズビアン」「ゲイ」「バイセクシャル」「トランスジェンダー」「クエスチョニング」の頭文字を取った言葉で、性的マイノリティを表す代表的な用語です。
レズビアンは女性に恋愛感情を持つ女性、ゲイは男性に恋愛感情を持つ男性、バイセクシャルは男女両方に恋愛感情を持つ人を指します。トランスジェンダーは生まれ持った性別と自分が認識する性別が異なる人、クエスチョニングは性的指向や性自認が定まっていない、または意図的に決めていない人を表します。
電通の「LGBTQ+調査2018」によると、日本におけるLGBTQ+に該当する人の割合は8.9%とされており、これは血液型がAB型や左利きの人とほぼ同じ割合です。なお、2023年の最新調査では9.7%という結果が発表されています。
アライが支援する理由
アライがLGBTQ+当事者を支援する理由は、多様性を認め合う社会の実現に向けた強い信念があります。性的マイノリティの人々は職場や学校で好奇の目で見られたり、差別的な言動を受けたりするケースが少なくありません。
また、カミングアウトできずに隠していること自体がストレスとなっている場合も多く、心理的な負担を抱えている現状があります。アライは当事者が安心して自分らしく過ごせる環境づくりを目指し、偏見や差別の解消に取り組んでいます。
さらに、すべての人が能力を発揮できる社会は、企業や組織の活力向上にもつながるという観点から、ビジネス界でもアライの重要性が認識されています。
参考記事: LGBTとLGBTQIの違いとは?そのほかのセクシャルマイノリティーを徹底解説!
アライとして何ができるのか
アライになりたいと思っても、具体的に何をすればよいのか分からない方も多いでしょう。アライとしての活動は特別なものではなく、日常の小さな行動から始められます。ここでは、実践的な支援方法を紹介します。
日常生活でできる支援行動
アライとして日常生活でできる支援行動は多岐にわたります。まず重要なのは、LGBTQ+について正しい知識を身につけることです。
書籍や映画、研修などを通じて学び続ける姿勢が必要で、無意識な発言で当事者を傷つけてしまわないよう注意が求められます。
具体的な行動としては、以下のような取り組みがあります。
- 性別を決めつけない言葉遣いを心がける(「お嬢さん・息子さん」ではなく「お子さん」と呼ぶ)
- 「男らしい・女らしい」ではなく「その人らしい」という表現を使う
- カミングアウトを受けた際は話をゆっくり聞き、当事者の同意なしに他人に伝える「アウティング」は絶対に避ける
- プライドイベントやアライ関連の活動に参加する
これらの行動は特別なスキルや資格を必要とせず、誰でも今日から始めることができる支援活動です。
参考記事: 「LGBTフレンドリー」・「アライ」とは?意味や役割を徹底解説!
職場や学校での取り組み
職場や学校でのアライ活動は、組織全体の意識改革につながる取り組みです。認定NPO法人虹色ダイバーシティの調査によると、職場にアライがいるLGBT当事者は心理的安全性が高いという結果が示されており、アライの存在が職場環境に与える影響の大きさが証明されています。
具体的な取り組みとしては、LGBTQ+に関する研修の実施、性的マイノリティ向けの福利厚生制度の整備、アライであることを示すステッカーやバッジの配布などがあります。また、性別に関わらず使用できるトイレの設置や、パートナーシップ制度の導入など、制度面での改善も重要です。
教育現場では、多様な家族の形や性のあり方について学ぶ機会を提供し、差別やいじめの防止に努めることが求められています。組織全体でアライを増やすことで、LGBTQ+当事者が安心して能力を発揮できる環境づくりが可能になります。
企業と自治体のアライ推進事例
近年、多くの企業や自治体がアライ推進に積極的に取り組んでいます。野村證券では2009年からダイバーシティ&インクルージョンの一環としてアライ活動を開始し、「LGBTA」と表記してアライの「A」を加えた独自の取り組みを展開しています。
LGBTに関するイベントへの参加・協賛、虹色の卓上コーンやステッカーの配布など、可視化された支援活動を行っています。ギャップジャパンでは2018年に全従業員向けのアライトレーニングを開発し、研修後にアライ宣言をした従業員にピンバッジやステッカーなどのグッズを配布しています。
自治体では、埼玉県が2024年5月に「アライ コバトン&さいたまっちマグネットステッカー」を作成・配布し、企業の取り組み状況を県の公式サイトで公表するなど、積極的な支援を展開しています。東京都も「TOKYO ALLY」マークを作成し、アライを広める取り組みを推進しています。
アライが当事者に与える影響
アライの存在は、LGBTQ+当事者にとって計り知れない安心感と支えをもたらします。一般社団法人work with Prideの「LGBTQ+ アライガイドブック」に掲載された当事者の声によれば、アライは「カミングアウトする、しないに関わらず、職場で安心感を与えてくれる存在」「安心して自分らしく働ける職場の雰囲気や風土を作る大きな力であり、心強い存在」として評価されています。
認定NPO法人虹色ダイバーシティと国際基督教大学ジェンダー研究センターが実施した「niji VOICE 2020」調査によると、職場にアライがいるLGBT当事者は、そうでない当事者と比較して心理的安全性が高いという結果が示されています。
アライが増えることで、当事者は自分の性的指向や性自認を隠さずに生活できる環境が整い、ストレスの軽減や生産性の向上につながります。また、アライの存在により、無意識の差別や偏見が可視化され、組織全体の意識改革が促進されるという効果もあります。
当事者にとってアライは、社会とのつながりを感じられる重要な架け橋の役割を果たしているのです。
参考記事: アライ(Ally)とは?LGBTの不安や迷いに優しく寄り添えるのがアライ
日本と世界のアライ推進状況
アライの概念は国境を越えて広がっており、各国で独自の取り組みが展開されています。日本と海外の状況を比較することで、今後の課題や可能性が見えてきます。
海外でのアライ活動の現状
アライの概念は北米から始まり、現在では世界各国で広がりを見せています。アメリカでは多くの企業でアライネットワークが構築され、アライトレーニングが義務化されている企業も少なくありません。
ヨーロッパでも同様の動きが活発で、特にイギリスやドイツでは政府主導でアライ推進政策が実施されています。カナダではプライド月間に合わせて、政府機関や大企業がアライ表明を行うことが一般的になっています。
アジア太平洋地域でも徐々に取り組みが始まっており、台湾やタイなどではアライコミュニティが形成されています。これらの国々では、アライが社会の多様性推進において重要な役割を担っていることが認識されています。
関連記事:
日本のアライ推進の課題と展望
日本におけるアライ推進は欧米諸国と比較するとまだ発展途上にありますが、近年急速に進展しています。2015年の渋谷区パートナーシップ証明書の導入以降、自治体レベルでの取り組みが拡大し、現在では400を超える自治体がパートナーシップ制度を導入しています。
人口カバー率は90%を超え、全国規模での理解促進が進んでいます。企業においても、東京オリンピック・パラリンピックを契機として、ダイバーシティ&インクルージョンの一環でアライ活動が推進されました。
ただし、職場でのカミングアウト率は依然として低く、当事者が安心して働ける環境づくりが課題となっています。今後は教育現場での取り組みや、中小企業でのアライ推進が重要なポイントになると予想されます。社会全体でアライの理解を深め、誰もが自分らしく生きられる社会の実現が期待されています。
参考記事: LGBTsの法整備どうなってる? 日本や世界の現状は?
アライになるための具体的な方法
アライになりたいと思っても、どこから始めればよいのか迷う方も多いでしょう。ここでは、段階的にアライとしてのスキルを身につけるための実践的な方法を解説します。
1.知識を身につける段階
アライになるための第一歩は、LGBTQ+に関する正しい知識を身につけることです。書籍や映画、ドキュメンタリーを通じて性的マイノリティの現状や課題を学びましょう。東京都が発行する「多様な性について知るBOOK」などの公的資料も参考になります。
また、LGBTQ+関連のセミナーやイベントに参加し、当事者の生の声を聞くことも重要です。知識を得る際は、偏見を持たず、先入観を排除して学ぶ姿勢が大切です。
間違った情報や古い認識を更新し、常に最新の知識を身につけるよう心がけましょう。インターネット上の情報は信頼性を確認し、公的機関や専門団体が発信する情報を優先的に参考にすることをお勧めします。
2.実践と表明の段階
知識を身につけた後は、実際の行動に移していきます。まずは身近な言葉遣いから見直し、性別を決めつけない表現を使うよう意識しましょう。職場や学校では、差別的な発言を耳にした際に適切に対応する準備をしておくことも大切です。
アライであることを表明する方法としては、SNSのプロフィール更新、アライステッカーの活用、プライドイベントへの参加などがあります。ただし、表明だけで終わらず、継続的な学習と行動が重要です。
当事者からフィードバックを受けた際は素直に受け入れ、改善に努める姿勢を持ちましょう。アライとしての活動は一朝一夕には身につきませんが、継続することで確実にスキルが向上していきます。
アライに関するよくある質問
アライについて多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。これらの質問と回答を通じて、アライに対する理解をより深めることができます。
自分もLGBTQ+当事者だがアライになれるか
LGBTQ+当事者であってもアライになることは可能です。むしろ、異なるセクシュアリティ間での相互理解を深めるために、当事者同士がアライになることの意義は大きいとされています。
例えば、ゲイの男性がトランスジェンダーの方のアライになったり、レズビアンの女性がバイセクシャルの方を支援したりする例が増えています。LGBTQ+コミュニティ内でも、すべてのセクシュアリティについて完全に理解している人は多くないため、お互いを学び支え合う関係性が重要です。
当事者がアライになることで、コミュニティ全体の結束力が高まり、より包摂的な環境づくりが可能になります。
アライ表明後に何もしなくても問題ないか
アライを表明した後は、継続的な学習と行動が期待されます。表明だけで終わってしまうと、当事者からの信頼を損なう可能性があります。
定期的にLGBTQ+に関する知識をアップデートし、差別的な言動を見かけた際には適切に対応することが重要です。また、無意識の偏見がないかを定期的に自己点検し、当事者の声に耳を傾ける姿勢を持ち続けましょう。
アライとしての責任を理解し、長期的な視点で支援活動を続けることが求められます。完璧である必要はありませんが、学び続ける意欲と行動力を維持することが大切です。
参考記事: lgbtqqiaappo2sとは?各セクシュアリティなど分かりやすく解説します!
まとめ:多様性を受け入れる社会の実現
アライは、多様性を受け入れる包摂的な社会の実現に向けた重要な存在です。性的マイノリティの人々を理解し支援するアライの活動は、善意の表明にとどまらず、すべての人が自分らしく生きられる社会の基盤づくりに貢献しています。
アライになることに特別な資格や条件は必要なく、正しい知識を身につけ、偏見を持たずに当事者を受け入れる姿勢があれば、誰でもアライとして活動できます。企業や自治体の取り組みも活発化しており、社会全体でアライを増やす機運が高まっています。
一人ひとりがアライとしての意識を持ち、日常の小さな行動から始めることで、誰もが安心して過ごせる社会の実現が可能になります。アライの輪を広げることは、多様性が当たり前に受け入れられる未来への重要な一歩となるでしょう。
参考記事:
- アライ(Ally)とは・意味
- アライ(Ally)とは?【LGBTQでなくても、今日から活動できる】
- Ally/アライとは?【LGBTQの支援者】意味を解説
- アライについて
- アライとは
- ally(アライ)とは?LGBTQなど多くの価値観を肯定 役割やなりかたを紹介
- アライとは――意味と事例、企業に求められるLGBTの理解者としての立場
- アライの意味や使い方
- TOKYO ALLY
- アライ(ally)
- 電通ダイバーシティ・ラボが「LGBT調査2018」を実施
- 電通グループ、「LGBTQ+調査2023」を実施
- LGBTと職場環境に関するアンケート調査 niji VOICE 2020 報告書
- LGBTQアンケート調査
- LGBTQ研修・コンサルティング
- NIJI BRIDGE
- 日本のパートナーシップ制度
- データで見るパートナーシップ制度
- LGBT当事者じゃなくてもできる。野村證券に聞く「アライ」を増やす取り組み
- ギャップジャパン全国約6,400人の従業員にLGBTアライトレーニングを実施